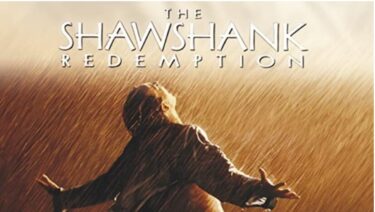東京ロイター
[東京 9日 ロイター] – 今週の東京株式市場は、神経質な展開が想定されている。米連邦公開市場委員会(FOMC)通過後も、米金融引き締め懸念は依然残っている。米国株が乱高下を続ければ、日本株も大きく振れそうだ。ただ、国内企業の決算発表がヤマ場を迎えるため、個別物色が下値を支えるとみられている。
日経平均の予想レンジは2万6300円─2万7300円。
3─4日に開いたFOMCでは、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標を0.50%ポイント引き上げたが、インフレ抑制には十分ではないとの見方がくすぶっており、一段の大幅利上げに対する懸念が出ている。週末6日の米国株は続落し、ナスダック総合は<.IXIC>は連日の年初来安値を更新した。
ドル高/円安傾向は、輸出関連企業にとって収益改善につながるなどプラス面に動いているものの、中国でのゼロコロナ政策による経済減速懸念、ウクライナ情勢の長期化といった材料は引き続き投資家心理の重しになっている。国内では企業決算が相次いで発表されているものの、市場では「決算内容以上に外部環境に対する警戒感があり、材料視されづらい」(国内証券)との声が聞かれる。
今週の主なスケジュールでは、米国で4月の消費者物価指数(CPI)と生産者物価指数(PPI)中国で貿易収支などの経済指標がそれぞれ公表される。国内では東京エレクトロン<8035.T>、ソニーグループ<6758.T>、ダイキン工業<6367.T>、任天堂<7974.T>、伊藤忠商事<8001.T>、三菱商事<8058.T>、資生堂<4911.T>などの主要企業が決算を発表する。そのほか、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)指数銘柄の定期見直しが予定されている。
市場では、外部環境に大きな変化がみられない限り、引き続き経済指標や企業決算をにらみながらの展開になるとの見方が優勢だ。「世界的な景気後退懸念がある中で、米金融引き締めが警戒されている。経済指標で弱い数字が確認されると、投資家心理が一段と悪化するだろう」(みずほ証券の三浦豊シニアテクニカルアナリスト)という。
企業決算については株価反応が二極化するとの見方が多い。企業が市場コンセンサスを上回る業績見通しを発表した場合、株価は素直に反応するとみられているものの、「先行きの不透明感が強い中、それに追い打ちをかけるような弱気な見通しが発表されると、売られてしまう」(東洋証券の大塚竜太ストラテジスト)という。
R4.5.9
[東京 9日 ロイター] – 東京株式市場で日経平均は、前営業日比684円22銭安の2万6319円34銭と、大幅に反落して取引を終えた。米長期金利の上昇や新型コロナウイルス感染拡大による中国経済への悪影響が警戒され、幅広く売られた。ロシアの戦勝記念日にあたり、プーチン大統領による演説への警戒感も重しになった。
大型連休明けの日本株は軟調な展開となった。前週末の米株安を嫌気する形で安く寄り付いた後も、下げ幅を拡大した。米長期金利の上昇が投資家心理の重しとなり、ハイテク株や高PER(株価収益率)株など幅広く売られた。一部でロックダウン(都市封鎖)が続く中国経済の先行きへの懸念も重しとなった。この日はロシアで第2次世界大戦の対ナチス・ドイツ勝利を祝う戦勝記念日にあたりプーチン大統領の演説が予定され「ウクライナ情勢を一段と緊迫化させるような発言が警戒される」(国内証券)との声も聞かれた。日経平均は大引けにかけて徐々に下げを拡大し、一時694円34銭安の2万6309円22銭の安値をつけた。日経平均のPERは12倍台で割安とされるものの、米金利上昇に伴う米株安への警戒感が続いている。市場では「先週の日本株は相対的に堅調だったが、米株安となれば、
やはりついていかざるをえない。外部環境が好転していない中で、買い向かう理由は見当たらない」(水戸証券の酒井一チーフファンドマネージャー)との声が聞かれた。今週は主要企業の決算発表を控えていることも、様子見につながりやすかった。
TOPIXは1.96%安の1878.39ポイントで取引を終了。東証プライム市場の売買代金は2兆9545億5500万円だった。東証33業種のうち値下がりは30業種で、値下がり率上位には鉄鋼や空運業、サービス業などが並んだ。値上がりは電気・ガス業、海運業、石油・石炭製品の3業種だった。高PERのエムスリー<2413.T>やキーエンス<6861.T>が軟調だったほか、指数寄与度の高いファーストリテイリング<9983.T>やソフトバンクグループ<9984.T>がさえなかった。日本郵船<9101.T>も安かった。一方、大規模な自社株買いを発表したヤマダホールディングス<9831.T>はストップ高となった。東証プライム市場の騰落数は、値上がりが211銘柄(11%)、値下がりは1598銘柄(86%)、変わらずは28銘柄(1%)だった。13461
R4.5.10
[東京 10日 ロイター] – 10日午前の東京株式市場で日経平均が心理的節目となる2万6000円を下回り、3月16日以来の低水準に下落した。米国での金融引き締めや中国景気の減速への懸念がくすぶる中で売り圧力が強まった。
[東京 10日 ロイター] – 東京株式市場で日経平均は152円24銭安の2万6167円10銭と、続落した。前日の米株急落の流れを受け、朝方は心理的節目の2万6000円台を割り込む場面がみられたが、その後下げ渋った。時間外取引で米株先物がしっかりと推移したことを受け、米国株の下げ止まりや反発への期待が支えとなった。
9日の米国株式市場は10年債利回り<US10YT=RR>が3年半ぶりの高水準に達し、ナスダック総合<.IXIC>が連日の年初来安値を更新。日本株もハイテク株を中心に幅広く売られ、一時545円51銭安の2万5773円83銭で安値を付けた。その後は原油価格の下落や時間外取引での米株先物の底堅い値動きが支援材料となり、日経平均はじりじりと下げ幅を縮小する展開となった。
市場では「割安感が意識され始め、直近で安値を付けた銘柄はしっかり。インバウンド需要の回復、価格上昇を見越した駆け込み需要などの期待感もあり、地固めのフェーズに入ってきている」(アイザワ証券坂瀬勝義国内情報課長)との声が聞かれた。
TOPIXは0.85%安の1862.38ポイントで取引を終了。東証プライム市場の売買代金は3兆2345億9700万円。東証33業種では、鉱業、卸売業、海運業、石油・石炭製品などの22業種が値下がり、金属製品、電気・ガス業、ガラス・土石製品などの11業種が値上がりした。
個別では、NTTデータ<9613.T>が7%超安と大幅安となったほか、東京エレクトロン<8035.T>、ソフトバンクグループ<9984.T>、アドバンテスト<6857.T>などの値がさ株が日経平均を押し下げたほか。ソニーグループ<6758.T>は3%超安と年初来安値を更新した。原油価格の下落を受けて、INPEX<1605.T>も7%超安となった。半面、回転すしチェーンの「スシロー」の商品値上げを発表したFOOD & LIFE COMPANIES<3563.T>はプライム市場の値上がり率トップ。良品計画<7453.
T>、川崎汽船<9107.T>も買われた。値がさ株ではファーストリテイリング<9983.T>、ダイキン工業<6367.T>がしっかりだった。プライム市場の騰落数は、値上がり704銘柄(38%)に対し、値下がりが1062銘柄(57%)、変わらずが71銘柄(3%)だった。13461
R4.5.11
[東京 11日 ロイター] – 東京株式市場で日経平均は小反発。前日比46円54銭高の2万6213万64銭で大引けた。米国で4月の消費者物価指数(CPI)が公表されるため、それを見極めたいとのムードがあり、模様眺め気分が広がった。10日の米国株式市場は、S&P総合500種<.SPX>とナスダック総合<.IXIC>が上昇して終了。米国債利回りが低下する中、前日に売られた大型成長株が買われた。
日本株は売り優勢で始まったものの、時間外取引で米株先物が堅調に推移したことから徐々に持ち直し、中盤以降はプラス圏でのもみあいとなった。ただ「米国でCPIが公表されるため、様子見姿勢が強い」(野村証券・投資情報部ストラテジストの神谷和男氏)との声も聞かれ、積極的に上値を買う動きはみられない。
一方、後場に入って、トヨタ自動車<7203.T>が今期は減益見通しになるとの決算を発表したが、相場全体への影響はほとんどみられなかった。同社は決算発表後に売られたものの、そのほかの個別銘柄では、決算と同時に株式分割を発表した任天堂<7974.T>、自社株買いを発表したソニーグループ<6758.T>が物色され、日本製鉄<5401.T>も高い。TOPIXは0.60%安。東証プライム市場の売買代金は、3兆2045億4700万円だった。東証33業種では、海運業、鉄鋼などが上昇した半面、保険業、輸送用機器、銀行業などの下げが目立つ。プライム市場の騰落数は、値上がり629銘柄(34%)に対し、値下がりが1138銘柄(63%)、変わらずが50銘柄(2%)だった。13460
R4.5.12
[東京 12日 ロイター] – 東京株式市場で、日経平均は前営業日比464円92銭安の2万5748円72銭と大幅に反落して取引を終えた。米国市場での株安が相場の重しとなり、一時500円超下落した。売り一巡後は下げ渋る場面もあったが、戻りが一服すると、午後にかけて上値の重い展開が続いた。日本株は、米株安の流れを受けて朝方から売りが優勢となり、一時前525円53銭安の2万5688円11銭の安値をつけた。ハイテク株比率の高い米ナスダック総合の大幅安が重しとなり、半導体装置関連株や高PER(株価収益率)株が軟調となった。
TOPIXグロース指数は1.82%安で、同バリュー指数は0.62%安だった。新興株式市場は、マザーズ総合が6.07%安と大幅に下落し、2020年4月以来の安値となった。日経平均は、売り一巡後に買い戻しが活発になり、下げ渋る場面もあった。ただ、ウクライナ情勢や中国景気の先行きへの警戒感がくすぶるなど外部環境の不透明感が継続しており、戻りが一巡した後は、再び上値が重くなった。市場では「円安を踏まえると中期的に上方向が見込めそうだが、目先の市場は不安定な状況が続く可能性があり注意が必要」(東海東京調査センターの仙石誠シニアエクイティマーケットアナリスト)との声が出ていた。米国での金融引き締めへの警戒感が継続する中、前日発表された4月の米消費者物価指数(CPI)の結果は、インフレがピークを打った可能性を示したものの依然として高く、米利上げや経済を巡る投資家の懸念を払拭するには至らなかった。
TOPIXは1.19%安の1829.18ポイントで取引を終了。東証プライム市場の売買代金は3兆2683億9200万円だった。東証33業種では、値下がりは情報・通信業やサービス業、水産・農林業など26業種だった。値上がりは、ゴム製品や保険業、石油・石炭製品など7業種。
個別では、ソフトバンクグループ<9984.T>やエムスリー<2413.T>、スズキ<7269.T>が軟調だった。一方、好決算を発表したオリンパス<7733.T>が堅調。SCREENホールディングス<7735.T>もプラスだった。東証プライム市場の騰落数は、値上がりが330銘柄(17%)、値下がりは1477銘柄(80%)、変わらずは30銘柄(1%)だった。13460
R4.5.13
[東京 13日 ロイター] – 東京株式市場で日経平均は前営業日比678円93銭高の2万6427円65銭と、急反発した。積極的な買い材料に欠けるものの、 ショートカバー(売り方の買い戻し)に加え、オプションSQ(特別清算指数)に絡んだ売買も交え、踏み上げ相場となった。個別では、日経平均の指数寄与度の高いソフトバンクグループ<9984.T>、東京エレクトロン<8035.T>、ファーストリテイリング <9983.T>が大幅高となり、3銘柄で日経平均を約323円押し上げた。きょうは5月限日経平均先物ミニ・オプションの最終決済に関わる日経平均のSQ(特別清算指数)算出日となり、ショートポジション解消で買い戻しを急ぐ動きが加速した。SQ値は2万5951円24銭となった。
日経平均は寄り付きで反発後、間もなく心理的節目の2万6000円を回復。その後も急速に上げ幅を拡大し、後場では731円21銭高の2万6479円93銭で高値をつける場面があった。時間外取引での米株先物が堅調に推移したほか、朝方からドル/円が円安水準で推移したことも支援材料となった。日経平均は前日に464円安となったこともあり、下落後の反動との見方もあった。
大和証券の末廣徹シニアエコノミストは「日経2万6000円を下回った水準では打診買いが入りやすいが、本格的な上昇基調からはほど遠い。今後の米市場の動向や中国のゼロコロナ政策などの外部環境は、引き続き懸念材料」との見方を示した。個別では、12日に赤字決算を発表したソフトバンクグループが悪材料出尽くし感から急反発し、12%超高。好決算を発表した東京エレクトロンは5%超高となった。そのほか、ファーストリテイリング、リクルートホールディングス<6098.T>、テルモ<4543.T>などの指数寄与度が大きい銘柄の上昇が目立った。半面、セコム<9735.T>、NTTデータ<9613.T>、トレンドマイクロ<4704.T>は下落した。TOPIXは5営業日ぶりに反発し、1.91%高の1864.20ポイント。東証プライム市場の売買代金は3兆5923億0800万円だった。東証33業種では、石油・石炭製品、精密機器、金属製品、電気機器、情報・通信業などの30業種が上昇。パルプ・紙、鉱業などの3業種が下落した。プライム市場の騰落数は、値上がり1557銘柄(84%)に対し、値下がりが259銘柄(14%)、変わらずが21銘柄(1%)だった。13460
来週は・・・
[東京 13日 ロイター] – 来週の東京株式市場は、強含みが想定されている。引き続き米金利の上昇懸念が強く環境面に不透明感が残るものの、日経平均で2万6000円以下の水準は底堅いことが確認された、との見方が出ている。下値に対する不安が徐々に和らいできており、下げた場面では買い優勢になるとみられる。3月期企業の決算発表が一巡したことを受け、好業績銘柄が物色されることになりそうだ。
日経平均の予想レンジは2万6000円─2万7000円。
米連邦準備理事会(FRB)はインフレ抑制に向けて、今後数カ月間で少なくとも3回、最低50ベーシスポイント(bp)の追加利上げを実施する見通しというのが、市場のコンセンサスとなっている。引き締め懸念から不安定な状態の米国株式市場に、今後も日本株が左右される場面がありそうだ。
ただ、下値模索を続ける米国株式市場に対して、日本株は3月安値を割り込まず、下値では底堅さを示すなど、明らかに米株と異なる動きとなっている。景気に対する不安が生じている米国と異なり、日本企業の業績見通しは円安も手伝い輸出関連企業を中心に好決算が目立つ。
「保守的な見通しが多い点を踏まえれば、企業業績は好調と言える」(岡地証券・投資情報室長の森裕恭氏)という。
テクニカル的にも底打ち感が生じているここからは、好調な企業業績を織り込む局面となりそうだ。東海東京調査センター・シニアストラテジストの中村貴司氏は「これまで下げ続けていたグロース株は、半導体を中心に業績上向きが確認されたため、上昇余地が大きくなった」と指摘する。
一方、引き続き懸念される材料としては、ロックダウンによって生じる中国の景気悪化に対する懸念だ。その意味で、当面のタイムテーブルでは、16日に発表される中国4月工業生産、同小売売上高などが注目を集めるとみられる。中国景気に対する不安が高まれば、相場はもうひと波乱ありそうだ。
- 1
- 2